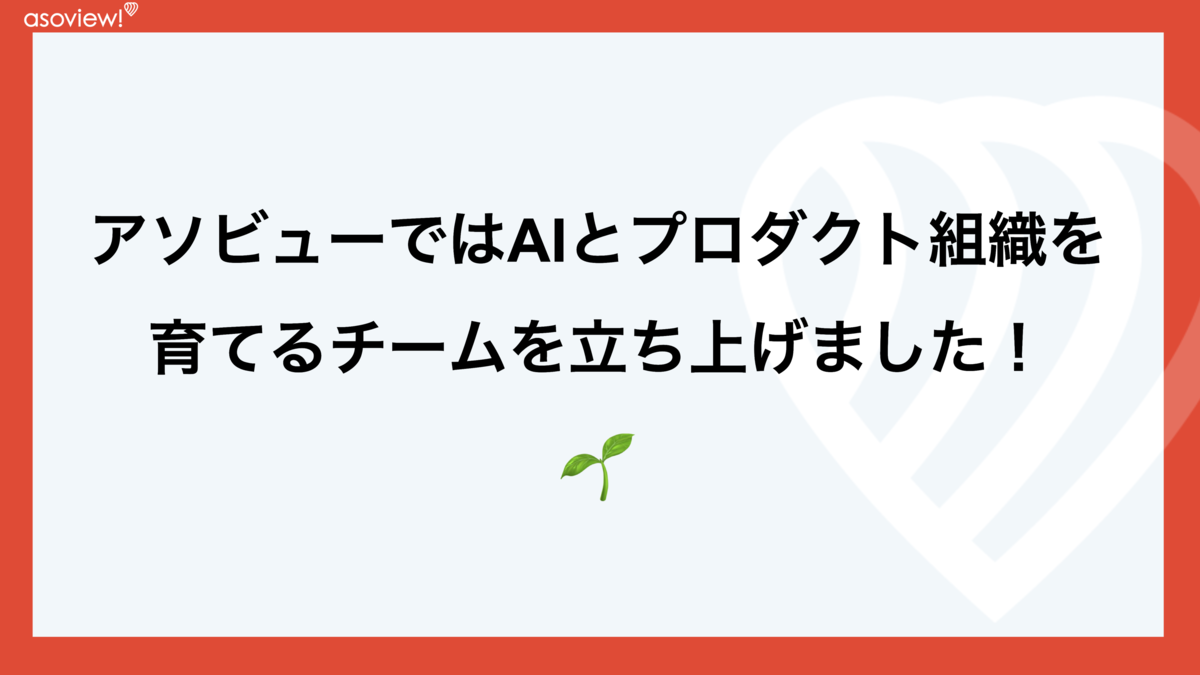
はじめに
こんにちは。アソビューCTOの兼平(@disc99_)です。
アソビューでは「生きるに、遊びを。」というミッションを掲げ、70兆円を超えると言われる余暇市場に向き合っています。

これらを実現していく上で、事業のコアとなるプロダクトを開発しているのが、プロダクト組織です。
既存事業のグロースと新規事業の立ち上げを並行で進めており、今後も既存事業はより大規模に、新規事業は多数立ち上がっています。
その中でも近年急速に発展するAI領域に素早く適応し、更に成長を加速させるため、全社横断のAI推進組織とは別に、4月よりプロダクト組織に特化したAIイネーブリングチームを立ち上げました!
現状の課題
プロダクト組織のAI活用の現状
現時点でアソビューでは、ChatGPT、Gemini、NotebookLM、GItHub Copilot、Devin、Cursor、Clineなど様々なAIツールを利用し開発を行っています。
これらの適応範囲は広く、コーディングなどの支援はもとより、コード解析によるナレッジ提供や問題調査、エラー・インシデント対応、テスト、ドキュメント生成・管理・PR作成やレビュー、要件作成など開発における幅広い領域で効果を発揮しています。
また、社内でも多数のナレッジが共有され知見を活かした新たなアプローチも多数生まれています。
私自身も数日かかる調査や検証を1〜2時間で解決する体験をしており、圧倒的な生産性向上を実感しています。
AIの進化スピードを考えると、今後さらに様々な活用が広がり、プロダクトにおいてより重要な役割を担っていくと考えています。
発生していた課題
社内でもAIを活用していく中、価値を感じるだけでなく課題も見えてきています。
個人主導の限界
開発者一人ひとりがキャッチアップしAI活用するアプローチは、素早く各々の業務に特化できる一方で、組織全体ではサイロ化や推進速度の問題が生じてしまいます。
ある人が当たり前に活用しているテクニックを、他の人は知らずに時間を掛けていることもあります。
組織全体に影響するような仕組みづくりを、プロダクト開発の限られた時間の中で同時に行う難しさもあります。
技術と事業ドメインの両方が急速に進歩する中、個人主導では機会構築をしたとしても限界がありました。
本番適応への壁
AIは圧倒的な速度でコード生成が可能ですが、GoogleのエンジニアリングマネージャーであるAddy Osmani氏の「70%問題」に代表されるように、本番環境に求められる品質に達しない課題もあります。 addyo.substack.com
アソビューでは新規プロダクトだけでなく大規模な既存プロダクトも存在するため、複雑なコンテキストを理解した最適設計も必要とされます。
意思決定の遅れ
根本的な課題になりますが、現在AIツールを活用している中で、もっと早く導入しておけばと思う機会がよくあります。
作業の効率化はもちろん、思考の整理など使い方次第で、数日や数週間レベルでの効果を発揮している場面も少なく有りません。
直近でこそ様々なツールを導入しているものの、一部に関しては導入に時間をかけてしまったものもあり、この意思決定の遅れは競争の激しい市場で大きな機会損失となります。
背景と目的
チーム立ち上げの背景
アソビューではAI活用を経営上の重要事項としており、早期から全社横断のAI推進組織を設置していましたが、今回更にプロダクト組織に特化したAIイネーブリングチームを立ち上げました。
エンジニアのあり方に関して様々な見解が世の中に溢れていますが、アソビューではDeNAの南場智子氏が発信されているように、この先もエンジニアの需要は増えていくと考えています。
logmi.jp
この状況の中一人ひとりがAIを活用しより力を発揮できる状態を作り、事業成長と生産性向上の加速することがプロダクトとして不可欠だと考えています。
また、このチームではCTOである私が直接マネジメントし責任を持つことで、意思決定のスピードを高め、組織全体へのAI活用推進をリードし、技術選定から導入、教育までのプロセスを素早く実現できる体制としています。
専任のチーム立ち上げは小規模なプロダクト組織であれば難しい部分もありますが、100名規模となったアソビューのプロダクト組織において、生産性が10%向上するだけでも、専任チーム設立の投資対効果は十分に見込めます。
現在のAI発展速度を踏まえれば、はるかに大きな成果が期待できると考えています。
育てる重要性
DevinなどのAIツールは「優秀なジュニアエンジニア」と例えられています。AIは万能ではなく、適切な情報と指示が不可欠です。
AIの力を最大限に引き出すには、得意・不得意を理解し、ベース知識となる情報整理やルール整備などの仕組みづくりが必要です。
またAI活用する人側も効果的に協働するスキルを身につけることで、AIの力を最大限発揮することができます。
新人に対して適当な指示や難しい業務を依頼すれば間違ったり、解決できないのは当然です。
逆に適切な指示を伝えることができれば圧倒的なスピードで成長していく事もあります。
これは新人エンジニアやマネージャー育成プロセスと多くの共通点があり、AI活用においても重要だと捉えています。
更に様々な分野で研究が進んでいるとおり、今後AIは人の学習や成長においても重要な役割を担っていくと思います。
チームの目的
新設したイネーブリングチームは、プロダクト組織全体のAI活用を加速させるため以下の役割を担います。
- AIツールの評価と導入支援:急速に進化するAI技術の中から、組織に最適なツールを検証し、投資判断をサポート。導入後も効果を継続的なモニタリング。
- ナレッジマネジメントの確立:AI活用に必要な社内ルールを整備し、ベストプラクティスやノウハウを蓄積・共有する基盤構築。
- 組織能力の強化:プロダクト組織内でのAI活用スキルを高め、チーム間での知見交換を促進。勉強会やワークショップを通じた学習機会の提供。
- プロダクトへのAI統合推進:プロダクトへのAI機能組み込みをリードし、技術的課題の解決策の提供。
- 部門間連携の窓口として機能:他部門とのAI活用における連携窓口として、組織全体でのAI活用推進。
専任チームがプロダクト組織のAI活用の中核となることで、推進力を確保しつつ、個々のメンバーによる日常的な工夫や発見もサポートします。
このチームの活動を通じて、プロダクト組織全体がAIを最大限活用し、本質的な課題解決、創造性にフォーカスできる状態を目指しています。
まとめ
AIツールの導入は容易に出来たとしても、それだけで効果を最大化出来るわけではありません。
アソビューでは、AIと組織双方の力を最大限発揮できる状態を育てるため、プロダクト組織に特化したAIイネーブリングチームを立ち上げました。
今後はAIの真価をより発揮し、プロダクト開発生産性を高め、事業成長と共に「生きるに、遊びを。」というミッションをより加速させていきます!
これからも大きく変化していくプロダクトを、AIを最大限活用して成長させていきたい方も大募集しています。
カジュアル面談もありますので、気軽にお声がけください!
www.asoview.co.jp